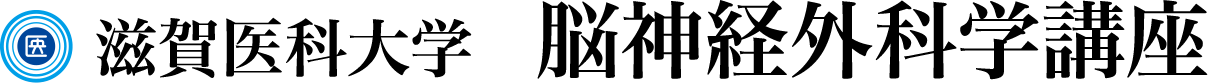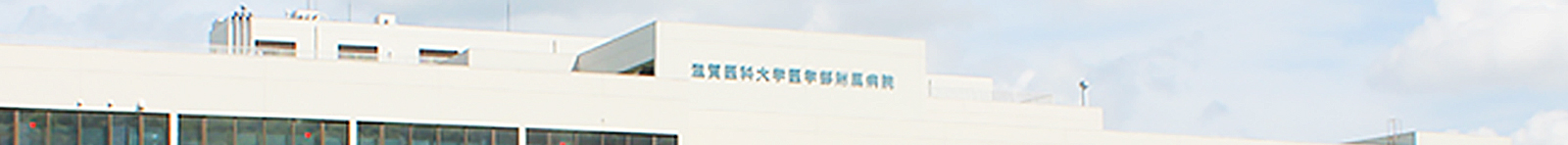
てんかん
てんかんとは、てんかん発作を繰り返す脳の慢性の病気です。てんかん発作とは、脳の中で、神経細胞が同時に、過剰に、異常興奮を起こしたことで生じる、一時的な症状(発作)のことです。
国際抗てんかん連盟の定義では以下の基準のうちいずれかを満たすものとなっています。1)24時間以上の間隔で2回以上の非誘発性の発作が生じる。2)1回の非誘発性発作が生じ、その後10年間にわたる発作再発率が、2回の非誘発性発作後の一般的な再発の危険性(60%以上)と同程度である。3)てんかん症候群と診断されている。
おおまかには、特に誘発する病気(高熱など)など無く、時間をおいて2回てんかん発作を起こすと、てんかんと考えられます。また脳卒中や脳炎、脳外傷では、病気や外傷後しばらくしてから、てんかん発作を1回起こすと再発率が高いことが知られており、てんかんと診断されて治療が始まる場合があります。
日本でのてんかんの発生率は年率で10万人あたり72人ほど、生後12ヶ月未満は最も多く、年率で10万人あたり200人ほど、次いで高齢者層が多く、年率で10万人あたり180人ほどでです。
てんかんは1000人あたり6人ほどが有しているとの報告があり、高齢者で多くなる傾向があります。日本には80万人ほどのてんかん患者がいると考えられます。
てんかんの原因はさまざまで、原因不明が多いですが、その他に脳出血などの脳卒中、アルツハイマー病などの変性疾患、脳腫瘍、脳外傷、脳炎などの感染があります。
初回のてんかん発作を起こした患者の33%は5年以内に再度発作を認めます。また2回目のてんかん発作を起こした患者の73%は4年以内に再度発作を認めます。てんかんと診断されても、薬物治療により70%の患者さんで発作が抑制されます。てんかん患者の死亡率は一般人口の2-3倍と言われています。
てんかん発作の種類
発作が一側大脳半球内の局所から始まるものを焦点起始発作、焦点から起始した後に両側大脳半球に広がって全身発作になるものを焦点起始両側強直間代発作、発作のはじまりから両側大脳半球がほぼ同時に巻き込まれるものは全般起始発作と言います。
てんかんの分類
焦点起始発作を起こす典型的なてんかんを焦点てんかん、全般起始発作を起こす典型的なてんかんを全般てんかんと言います。焦点てんかんと全般てんかんでは効果のある薬が違いますので、それらを見分けて、正確な診断をすることが重要になってきます。
てんかんの診断
てんかん発作の際の症状の解析、脳波検査、頭部MRIなどの画像検査の結果などから診断します。
脳神経外科の病気・外傷でのてんかん発作
脳神経外科に関連する病気・外傷としては、脳出血、脳梗塞、くも膜下出血、脳腫瘍、髄膜炎、脳挫傷などがあり、これらでは基本的に脳の局所に損傷があり、そこが焦点となって焦点起始発作を起こすことがあります。
病気・外傷の時期によるてんかん発作の分類
病気や外傷が起こって1週間以内(急性期)に認めた発作は急性症候性発作と言います。これが起きても基本的にてんかんとは診断しません。しかし病気や外傷から1週間以上経って安定した時期に起こった発作は非誘発性発作と言い、2回以上起こるとてんかんと診断されます。
焦点起始発作の抗てんかん発作薬
カルバマゼピン、ラモトリギン、レベチラセタム、ゾニサミド、トピラマートなどがあります。また新しいものとしてはラコサミド、ペランパネル、ブリーバラセタムなどがあります。
全般起始発作の抗てんかん発作薬
バルプロ酸が代表的です。
抗てんかん発作薬の継続
急性症候性発作の場合は、必ずしも発作は再発しないので内服中止は可能です。初回の非誘発性発作は原則として抗てんかん発作薬の治療は継続しませんが、脳卒中、脳炎、脳挫傷など、初回発作後に再発しやすいものでは治療継続を検討します。また高齢者も初回の非誘発性発作後、再発しやすいため治療継続を考慮します。
難治性てんかん
てんかんの患者さんの30%ほどが、薬でも発作が抑制できず難治性になることがあります。2-3種類の適切な抗てんかん発作薬でも、発作が1年以内に再発する場合、手術治療を選択する場合があります。具体的には、1)内側側頭葉てんかん、2)脳病変が存在する焦点てんかん、3)画像では脳の変化ははっきりしないものの、脳波やPET検査でてんかん発作の焦点が判別できた焦点てんかん、4)片側の大脳半球の広汎な病変がある焦点てんかん、5)脱力発作を持つ難治性てんかん、6)開頭手術の対象とはならない難治性てんかんで、迷走神経刺激療法の対象となるもの、などがあります。手術の適応は、長時間のビデオ脳波検査や複数の画像検査などを組み合わせて決定しますが、必要に応じててんかんセンターなどを紹介させていただいています。