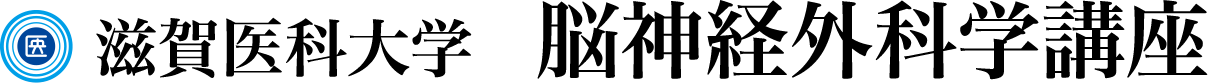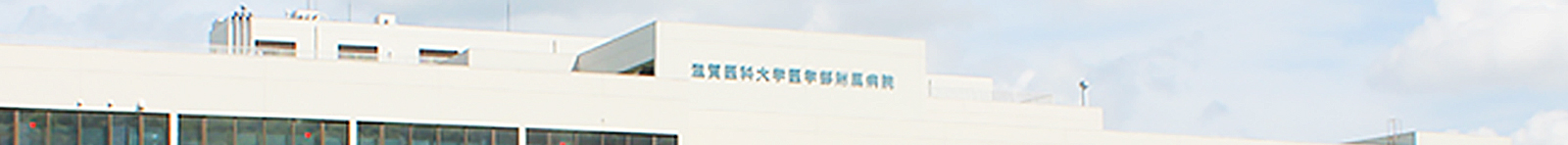
先輩の声
二宮 楓太(にのみやふうた)令和2年度卒業

2022年度に滋賀医科大学脳神経外科学講座に入局いたしました二宮楓太と申します。
愛媛県生まれ、大学も愛媛大学ですが、2年間の京都での初期研修時にたまたま滋賀医科大学脳神経外科の先生と知り合うきっかけがありました。もともと循環器内科や心臓血管外科などにも興味を持っておりましたが、そのきっかけを通じて脳神経外科の分野の幅広さや、学問としての奥の深さ、そして何より、顕微鏡手術から血管内治療、内視鏡や放射線治療まで同一科内で完結している点に魅力を感じ、脳神経外科を専攻することに決めました。
脳神経外科は腫瘍、脳血管障害、機能外科、外傷、小児、脊椎などの幅広い領域があり、それぞれの疾患に対して直達手術、血管内治療、内視鏡などの中から最善の治療法を選択し、単独または組み合わせて治療をすることができることが醍醐味の一つだと思っています。また、開頭一つをとっても、体位や皮膚切開、開頭の方法など、疾患や患者さんに合わせた工夫が必要であり、難しさと共に面白さを感じ日々研鑽に励んでいます。
現在私は脳神経外科学会だけでなく、脳卒中学会、脳卒中の外科学会、脳血管内治療学会、脳神経内視鏡学会、脊髄外科学会、脳神経外傷学会といった脳神経外科の関連学会に所属しており、それぞれの専門医/技術認定医の取得を目指しています。 脳神経外科といえば、手術が長く、緊急の処置が多いイメージがあるかもしれません。しかし近年、解剖や手技の解明や、道具の発達により手術時間も短縮傾向にあります。長時間の手術は途中交代を行うこともあり、また脳外科の代表的な手術は顕微鏡を用いて座って行うので特別な体力も必要としません。緊急手術やカテーテル治療は多いですが、若手に出番が回ってくることが多く、成長のチャンスもより多いといえます。分野が広いので、それぞれの希望や、ライフステージに合わせて働き方を選択することもできます。 滋賀医科大学脳神経外科の利点としては、症例数や上級医の数に比して専攻医の数が少なく、多くの症例を経験することができる点にあると思います。各関連施設では基本的に専攻医の配属は1人ですので症例に困ることはありません。 脳神経だけでなく外科系への進路を希望している方も、是非一度見学にきていただくことをお勧めします。脳神経分野は、現在もまだまだ発展している分野です。新しい時代の脳神経外科で皆さんと一緒に働くことを楽しみにしています。